違う意見があってもいいと考えるトレーニング
ロボット教室で、生徒と話しているときに気を付けているのは、このようなことです。
「ちがう意見=敵」と思ってしまう日本人には、議論をする技術が必要だ。
http://blog.tinect.jp/?p=41857
自分の意見はあっていいし、
好き嫌いは当然あるだろう。
人の行動で、理解できないこともたくさんあるだろう。
でもね。
それは、議論すべき相手ときちんと対話を重ねたらいいこと。
少なくとも教室には、議論すべき相手はいないことがほとんど。
となると、生徒同士で自分の好みを強制するか、
先生が、違う意見の子供たちが自分の意見を言わないように飲み込ませるか、
ということをしちゃいけない。
~~~~~~~~~
子供の意見を「口答え」
として、厳しくとがめられたことはあるかもしれない。
でもそれは、親、先生に、根拠がなかったから。
薄っぺらい理由を見透かされた気がして、
怒ることでごまかしていただけ。
~~~~~~~~~
学校も、家庭も、塾も、
対話の練習をするには、とてもいい場所だと思うのだ。
練習とは、
何度繰り返すこと、
失敗してもいいことになっていること、
試行錯誤すること。
練習するのは、子供だけじゃなく、
親も、先生も。
こういう時、立場は一緒。
一緒に練習していけばいい。
~~~~~~~~~
「ちがう意見=敵」の反対は、
「違う意見のあなたが意見を言う権利を、私は全力で守る」
こんな風に実感して、行動できるようにするには、
対話の経験を積んで、
いろいろな経験をしないといけない。
~~~~~~~~~
ロボット教室は、
集まっている生徒も先生も目的はだいたい同じなので、
練習の場にいいと思うんだ。
新しく来た先生向けの「心得」に、こんなことも書いてある。
「多少のエッチな話は構わないけれど、
生徒の意見を頭から否定することや、
自分の好みを宣言するなど、生徒が発言しにくくすることをしない」
(もちろん、セクハラは問題外)
お互いが、自由に発言できる場をつくりあうことが大切。
日常の場での練習、トレーニングは、繰り返しやらないとね。
関連記事
-

-
ロボットに子供の雑談相手をさせるには?
「ロボットやAIまだまだと言っても、子供の雑談相手とか、冷蔵庫からビール取ってきて注いでくれる的な雑
-

-
ロボット教室の生徒諸君10~まずは手伝う?自分の中から出てくるもの?~
まずはコチラを見てほしい。 ●10年かけた自作飛行機がついに飛んだhttp://porta
-

-
ロボット教室の生徒諸君 その4
こんな世界もあるぞ。 Siriを物理化したロボット動画に、技術者の愛を見た http://w
-

-
Vol. 103 [学習指導要領改訂案の生きる力、対話的、カウンセリング、キャリア、多様性]
〓〓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〓〓 Core Infinity 通
-

-
「自分の言葉では、まだ語れない」というしかない体験
> 「第二のふるさと」「宝物」といった言葉を使うのに抵抗がある。 > 「まだ、八坂での経験を消化
-

-
Vol. 87 [「天才」のまま生きていくために]
〓〓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〓〓 Core Infinity 通
-

-
「面倒くさい」と「やりきる」は別問題だよね
リンク先の記事と同じく、 「面倒くさい」 という生徒(ロボット教室)が多い。 中に
-

-
「受験数学」と「大学数学(または数学研究)」の違いは大きい
哲学な日々 考えさせない時代に抗し 野矢 茂樹 より。 ~~~~~~ (森毅先
-

-
ロボット教室の生徒諸君 その7~生徒のあなたたちに期待すること~
塾で、生徒のあなたたちに期待すること。 ①実験の事実を目で見て、純粋に「理科ってすごい」と思っ
-
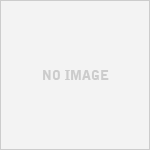
-
Vol. 33 [「目標」と心の機微]
〓〓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〓〓 Core Infinity 通信【Vol
PREV :
「やりたいことをやる」例・・・・大根の新品種
NEXT :
子供の攻撃性







