小中高校時代にも「自分で切り開く体験」をしよう
僕はロボット教室の運営をしているのですが、
生徒たちと話していると、どうしても 『塾』 のことを無視することはできません。
どこかモヤモヤしたものを感じていました。
「これかも」
と思う記事があったので紹介します。
名門校「武蔵」が守り切る「変わらない勇気」
塾歴社会「最後の楽園」の驚くべき実態
http://toyokeizai.net/articles/-/188426
~~~~~~~~~
受験勉強とはもともと、個々の受験生が自ら作戦を立て、自らを奮い起こして取り組むべきものであった。特に大学受験は、入試当日に至るまでのプロセスの踏み方を含めて、総合的人間力を試すものだった。
だが、ルールは変わった。
作戦立案は、塾のカリキュラムによって不要になった。自らに打ち勝つ意志力の代わりに、度重なる塾のテストが受験生を勉強へとかき立ててくれるようになった。より効率のよい戦い方が模索されるうちに、本来受験生自身に求められていた能力の大部分を塾が肩代わりするようになったのである。
“結果にコミットする”スポーツジムに似ている。トレーナーが完璧なメニューを用意して、それをやり切るまで追い込んでくれるシステム。トレーナーの指示にいちいち自分の考えなど差し込まなくていい。ただ従順に言われたとおりにやっていれば、筋肉がついたり、減量できたりする。
その結果、受験生に求められるものとして、大量の課題をこなす処理能力と忍耐力だけが残った。余計なものとしては、与えられたものに対して疑いを抱かない力が求められるようになった。
(リンク先より引用)
~~~~~~~~~
塾は、経験値を積み重ねてシスティマチックに、
合理的に、効率的な
「受験勉強の戦い方」を提供してくれる。
「言われたとおりにやればよい」
「大量の課題をこなす処理能力と忍耐力、
疑いを抱かない力が求められる」
と分析されている。
---------------
現状がどうかは、残念ながら断定できるほどの情報を持っているわけではない。
が、モヤモヤした感じを言い表しているようにも思えました。
「勉強」
って、本来は自分の目標に向かう中で、
自分で計画し、自分の力を測って、
やり方も含めて試行錯誤するもの。
「だって、やりたいことだから」
が本来の姿だと思うのですが、
試行錯誤や
挫折
が、大切な人生経験になる、
というか、それが「勉強」というものだと思っているからです。
それじゃ、「生きる力」が身につかないよね。
自分が別の新しい課題に出会った時、
誰も「完ぺきなメニュー」なんて作ってくれません。
『大量の課題をこなす処理能力と忍耐力、疑いを抱かない力』
だけの人を仲間にしたいと思いません。
---------------
まあ、あるものは使わせてもらえればいいけれど、
小中高校時代にも、
「自分で切り開く体験」
をぜひしてください。
今までしていなかったとしても、
これからはじめればOK。
関連記事
-

-
滋賀県草津市周辺の子供たちが学ぶ場の情報
滋賀県草津市周辺の子供たちが学ぶ場の情報。 若狭視点でのセレクション。(2016.12.20現在)
-

-
人は意味を考えている?関係を見ている?
AIの弱点は「意味の理解」 東ロボくん研究・新井紀子さん 寄稿記事。 AIは、パターン分析を
-
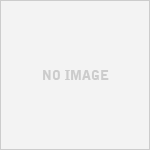
-
Vol. 5 [スケートを簡単に上手に滑るには?]
若狭 喜弘(Yoshi)です。 【スケートを簡単に上手に滑るには?】 冬季オリンピックが終わり、
-

-
成功と失敗をどういう風に表現するか?
日本「打ち上げ失敗」アメリカ「partial success」 pic.twitter.com/jW
-

-
「学びラボ ロボット教室」の先生は、雑談が仕事?
かつて生徒から、 「先生は教えないねえ。雑談ばっかりだねえ」 と言われたことがあります。
-

-
「学び」を呼吸と同じように無意識にできるようになるために・・・
同じ勉強をしていて差がつく「本質的な理由」http://toyokeizai.net/article
-

-
「子供の学習習慣をつけさせる」ために方便として「強制」も必要?
「子供の学習習慣をつけさせる」 というと、 「毎日机に〇時間座らせる」 「学校から帰っ
-

-
学ぶときに手を抜こうとする・・・と?
ひきたさんコラム 机の前に貼る一行 (朝日学生新聞社) - LINEアカウントメディアhttp://
-

-
Web動画『学校を飛び出した子供たち_フリースクールのすごさ』
学校を飛び出した子供たち_フリースクールのすごさ20160220houdoutokusyuhttp:







