学校で、書類を増やすより、授業内容をワクワクしながら変えていくには
公開日:
:
最終更新日:2017/03/07
et cetera-life, et cetera-opinion, 子供達の学ぶ心
> 今の改革は大学にアリバイづくりの大量の文書作成を促すだけで、肝心の授業内容はあまり改善されていない。
(経済気象台)変わる大学教育
先日公表された学習指導要領改訂案を読んだ時に感じたこと。
改訂案自体は、よく考えられたものだと思った。
けれど、そこで力尽きているような印象がある。
「新しい授業提案」をし、
さらに「大量の文書作成」をする仕組み
になっているような気がする。
生徒も多様、
先生も多様、経験年数も多様、能力も多様
それを、「学習指導要領」という通達や上が考えた仕組みでうまくいくのだろうか、と思う。
「ゆとり教育」のまとめも、間違った評価法で結論を導いているように思われる。
人の生命だから、「失敗してもいい実験」というのはあり得ないが、
もう少し科学的な検証をした方がいい。
その時の評価軸を、実力テスト、PISAなどとするか、
進学率とするか、
海外進学者数とするか、
正社員雇用率とするか、
GNP、GDPとするか、
大学に社会人入学する人数とするか、
何を評価軸にしたら、いいのだろう?
でも、それらはあくまでも「手段」
人が生きるために使う「道具」
生活する国の「基盤」「インフラ」。
そんなものが高くても、
「幸せ度」「人生の満足度」
は関係あるだろうか。
少なくとも、学校の先生が不要な書類書きをする時間を、
生徒への指導法研究に充ててもらいたいものだ。
単に教科書の中身をわかりやすく教えるとか、
単元の中身を面白がらせるとか、
も大事。
「自分で課題を設定して、学んでいこうとする姿勢」
学校が、これを身につけられるような機会になるといい。
そのためには、「先生のやるべきこと」
「先生の働き方」
「学ぶ環境づくり」
これらが大幅に変わる必要がある。
関連記事
-

-
日常、何を買うのかということも十分に政治的だ
> 俺から言わせれば、日々の生活のなかで何を買うのかということも十分に政治的だ。 > 後藤正文
-

-
自分は何に共鳴してその仕事をしたいのだろうか
やりたいこと、っていいながら、結局なにかの「職業」につきたいだけということはある。でも、その「職業」
-

-
ディベートとダイアログ
敗戦の日にあたり、国内も国外も、 「私が正しい」と思い込みの評価だったり、捏造した事実だったり
-

-
理論を知っていても、過去のできごとを知っていても・・・
天才テスラも驚愕? カーボンナノチューブが勝手に電気回路を作り上げたhttp://www.newsw
-

-
熊蟄穴(くまあなにこもる)
七十二節季では「熊蟄穴(くまあなにこもる)」です。 熊は冬が来るまでにたくさん食べ、メ
-

-
お酒を久々にいただきます
Osaka sake / rei-san[/caption] 今日はお酒を飲める日。
-
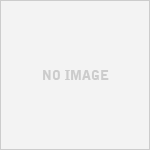
-
「安くないと消費者は買ってくれない」って本当?
「安くないと消費者は買ってくれない」 この状況からの脱却を謳って、現在、日銀の施策は円の市
PREV :
すべてが物語にされる
NEXT :
「土と海の汚染と同じ汚染が、自分の身体にも起こっている」









