「教育の情報化(ICT化)」を横目で見て思うこと
公開日:
:
et cetera-opinion, 子供達の学ぶ心
貧困層の子どもたちにパソコンを与えることが、教育問題解決となるのか?
http://nge.jp/2016/12/09/post-136572
日本でも取り組みがあります。
教育の情報化の推進
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/index.htm
しばらく前まで「ICT化」と言っていましたが、
最近は「教育の情報化」という言い回しになっているようです。
僕は、
「当然だな」
としか思えない結果です。
~~~~~~~~~
実際に現場では、どこでも同じことが起こっています。
・IT機器で、ゲームをする。
・IT機器で、動画を見る。
・IT機器で、SNSにつなぐ。
その理由として、
・IT機器を知らない生徒は、使い方を全く分からないので何もできない。
・IT機器の使い方を知っている生徒は、興味の方向に従って使う。
・(生命の危険がない状態だと)人間の興味の方向は、「食欲」「遊び」「性欲」「睡眠欲」である。
(「学習欲」の順位はかなり下がる)
これを、論理的に、思考で、善悪で叱っても仕方ありません。
人はそんなものでは動きません。
大人でさえ、FacebookやTwitterに頻繁にアクセスし、
Instagramに投稿する写真を撮るために食事をしたり、人と会うような
本末転倒なことをしているのですから。
もし、「学習させたい」ならば、
・学習することに飢えさせる。
・学習することと生きることを直結させる。
・学習することしかできない、生徒が見たことがないまったく新しい機器を使う。
ココまで考えると、
『学習するのは手段。
だったら、目的は何だ?
それが伝わっていないし、
生徒と共有できていないぞ』
とたどり着きます。
僕の個人的な意見なんですが、
「ゲームのようにして学習させる」ことは、かなりレベルが低いところでとどまる。
と見ています。
一つの正解に向けて、IT機器に判定させることでしかない。
たくさんの正解、たくさんの道筋があることに気づかせるのが教育じゃないか?
IT機器だと、
もし「たくさんの正解」を出させようとしたら、
そのプログラムを作った人が考えた範囲の、
「たくさんの正解」でしかありません。
では、道具としてIT機器はどうか?
確かに、IT機器でしかできないことはある。
それまで先生が手作りしていたことを、
全国で、きれいに整えられたものを使うことができる。
でも、そうしたら、当日、
先生が生徒の顔を見て内容や使い方変えることはできないし、
もともと先生がやっていたことだったら、
IT機器にこだわる必要はない。
~~~~~~~~~
「教育の情報化」に携わっている人に聞くと、
(その人はITの専門家で、教育の専門家ではない)
・使い方を教える。
・勝手なことをしている生徒を叱るか、放置する。
と聞きました。
機材としても、
企業にOA環境が入っていき、
一人に1台になっていく段階で、
様々なトラブルが発生したのと
同じことが起こっているようです。
(僕がかかわるロボット教室でも、
パソコンからロボットにプログラムを書き込めないトラブルが
かなりの頻度で発生しています。
なおかつ、原因不明です。)
~~~~~~~~~
学校では、
・IT機器の使い方を教えること
・(IT機器を使うことを含めて)学ぶことにワクワク感を持たせること
・生徒から出てくる、発想を出させ(評価しないで)、さらに伸ばすこと
を、段階別にグループに分けるしかないのじゃなかろうか。
ただし、
「ワクワク感」
「発想」
これは、生徒によって方向が全く違う。
音楽に興味を持つ生徒
プログラムに興味を持つ生徒
ゲームに興味を持つ生徒
算数・数学に興味を持つ生徒
理科の科目に興味を持つ生徒
社会の科目に興味を持つ生徒
これまた一緒くたにはできない。
~~~~~~~~~
また根源的なことを書きます。
●学ぶとはどういうことか?
●学んだらどうなるのか?
●それが自分にどういう意味があるのか?
これがないと、ただの野放図になります。
できたら、先生も生徒も、
一緒にディスカッションして、
共通の理解にしておきたい。
できなかったら、先生だけでも、これの自分なりの答えを持っておきたい。
きれいな、
上司や教育委員会、文部省、保護者、マスコミなど外向きに受けがいい答えじゃなくて、
本音の答えね。
それを元に、先生同士でも、
「正誤」をジャッジするのではなくて、
本音でディスカッションしてほしい。
IT機器は、道具でしかありません。
文章、絵、音楽、プログラムなど
一部に使っても
自分を表現するための道具にもなります。
一方では、
ゲームやSNSなど、
閉じた世界で、さらに世界をどんどん狭くする道具にもなります。
(それらも決して悪いものじゃないけれど)
職人は、道具にこだわるけれど、
それは、自分の指先をさらに伸ばすための道具でしかない。
だから、道具のその時の状態を受け入れるけれど、
自分が使いやすいように常に整え続ける。
(包丁を研いだり、電池を交換したり、劣化した部分を修理したり・・・)
教えるなら、それを教えなきゃならないんだけれど、
教えやすいことから、
教えやすいことだけ
「教えよう」とするからね。
教える人が、「教えること」の先を探求しないと。
『「教え方」や「知識」を教わろう』
としている段階から、先に行ってほしい。
もし、それが難しいのであれば、
できる人材にやってもらうために、
『教育にはお金がかかる』
として、国や自治体、保護者も支出が増えることを覚悟してほしいなあ。
こんなのは、「資格制度」「研修」で何とかなる性質ものではないと思う。
「研修」は、発注者、講師ともに、その気になれば変わるが。
関連記事
-

-
ロボット教室の生徒諸君11~「学ぶ」ということ~
仕事や学校だと 「失敗したくない」 と、やる前からあきらめてしまうかもしれないけれど、
-

-
東日本大震災3年目の日に
Praying Gopher / danelow[/caption] 3年前のあの日、 今
-
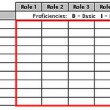
-
「コンピテンシー」余話
Measure Competency Importance for Each Role / den
-

-
「では子どもたちは「読めて」いるのか?」
AI研究者が問う ロボットは文章を読めない では子どもたちは「読めて」いるのか?http://byl
-

-
子供たちって、意外に創作を苦手に思っている?
「日本人がまた変なもの作ってる…」世界中で大ウケの工作家・乙幡啓子さんhttps://irorio.
-

-
勉強するってこういうこと・・・アリの研究を例にして
大学・・・・だけじゃないけれど、研究することの面白さを紹介しよう。 「勉強する」って、すでにわかっ
-

-
Web記事「別れのコーチング」「密室性」「対人性」
コーチングの「スキル」ではない「暗黙の了解」の話。 クライアント獲得につながらないコーチングの話題
PREV :
「自分の言葉では、まだ語れない」というしかない体験
NEXT :
「学び」を呼吸と同じように無意識にできるようになるために・・・










