「教育」を実験してもいいじゃないか
公開日:
:
最終更新日:2016/06/03
et cetera-opinion
> 教育はもつとも実験室化してはならぬものでありながら、もつとも実験室化しやすいもの
> 福田恆存
(選・鷲田清一)
折々のことば より
教育は「実験室」というか、
サービスを受ける人たちは、圧力団体になれず政治と交渉できないし、
その学年は、その1年間しかいられない。
それに学校でカリキュラムは、「同じ内容」には2度と出会わない。
だから、どうしても
実験室の中の実験動物になってしまう。
でも、「教育力の向上」のためには、
それ以外の点では「実験室」でもいいんじゃないのかな、と思う。
だって、「試行錯誤」「チャレンジ」は誰にとっても必要なもの。
先生にとっても、行政を決める人たちにとっても。
学生に
「受け身でいて、
被害者意識を持つ暇があったら、
考えて行動しろ」
というメッセージを出せばいいだけじゃないか、と思う。
「実験」がダメだったら、
先生の渾身の工夫の塊「研究授業」などできない。
「ゆとり世代・ゆとり教育」と揶揄されがちだが、
教育はけっして悪くなかったと思うけどね。
もっとも、その中の核
「学ぶとはこういうこと」
が、学んだ人たちに伝わりきっていないように思われるのが残念ではある。
~~~~~~~
ただ、「教育」という名の、
個人の、学ぶ生徒一人一人が主語でない、
「国は」といった、『国の目的』に沿った教育方針で行う
「刷り込み」
「枠はめ」
「規格化」
は、止めてほしい。
と切に思う。
愛されたかったら、愛されるようになればよい。
「我慢する」のではなく、
「自然体で」
「相手に応じて」
「相手を尊重して」
国を作っていったら、
誰からも愛されるのではないか?
力の強さは関係なく、
「自分を信じる心」の強さがあればいい。
そのためには、
「相手を変えようとする」のではなく、
「自分の姿を自覚し」
「ありのままの姿を、自分で愛する」
ことじゃないか?
「人」も「国」も同じだね。
関連記事
-
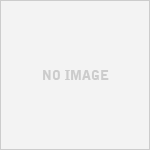
-
「アイスブレイク」と「ブレイク・ジ・アイス」
「事務局運営のコツ for coach, consultant and counselor
-

-
ノウハウが蓄積されたので、プロに任せなくても・・・・本当?
> 「年々、音楽事務所の占める割合が小さくなってきていてこれまでの経験から音楽祭のノウハウが蓄積され
-

-
「選挙」って、「社会の多様性」を映すもの
選挙のことで、やっとわかったことがあります。 今まで、「変だな」と思っていても、「問い」の形に
-
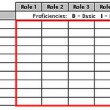
-
「コンピテンシー」余話
Measure Competency Importance for Each Role / den
-

-
みんなの中で共通する無意識
> 「僕はね、集合的無意識にアクセスしたいと思っているんですよ」 (一語一会)映画プロデューサー・
-

-
「ロボット教室基金」の枠は作れる
> 破れてなかみのなくなった畳が畳であり、菜のない食事が食事であり、玩具のない遊戯が遊戯である。
-

-
「人間の中に『好き』と言う感情があるから、戦争がなくならない」
魔法のコンパス 道なき道の歩き方, 西野 亮廣 より 未読です。 この本の中に、タモリさんの
-

-
コーチングで子供たちに持ってもらいたいこと
教育現場や家庭でのコーチングはとても大切だと考えています。 「コーチングをする」ということではなく
-

-
「五輪開催5つのメリット」を考える
まず、 「五輪開催のメリット」と「五輪憲章」 この2つを混同してはいけない。 「五輪憲章」
-

-
Webの紹介『差別の種』
記事を紹介。 『差別の種 https://note.mu/harukazechan/n/nc
PREV :
おそらく人間の大多数は戦を望んでいない
NEXT :
社会のできごとを反省する?誰かを吊し上げる?







