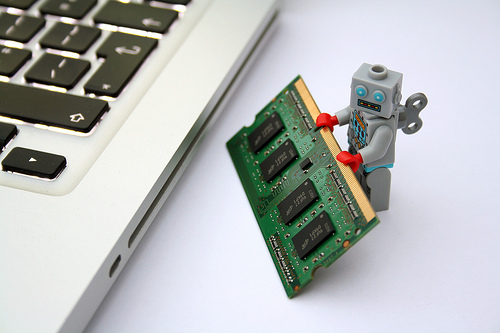10年先のロボット研究のテーマは何だろうか?
公開日:
:
最終更新日:2016/09/05
et cetera-life, 子供達の学ぶ心
東大から世界へ飛躍、自律型飛行ロボ「Phenox」がKickstarterプロジェクトを開始 – GIGAZINE http://gigazine.net/news/20140512-phenox/
ロボット教室関係で、私のアンテナに引っかかって収集した情報のメモ。
上記記事のヘリコプター(自立型飛行ロボ)は、コンパクトだからすごさが軽く見えるが、とてもすごいロボット。
日本のロボットが注目されたり、
その前にロボットを作っている人たちが発想力豊かにさまざまなものを想像しているのはいい。
魅力的。
でも、今の小学生たちが自分たちで作り出そうとする時期、
例えば、小学6年生が高校2年生や大学4年生になる、5年先、10年先に、
彼らが創造性を発揮できる状況が残っているだろうか?
もしくは新たなムーブメントが起こっているだろうか?
設計図通りに造るだけ、その範囲でつい実験をしたり、改良するだけでとどまってほしくない。
でも、
造船業や家電産業のように、大きな伸びがあった業界も、落ちる時期が必ずある。
その期間や落ち方は様々だけれど。
-----------------
スタート時点の話では、
ムーブメントの真っ最中は、というか、そのしばらく前から、
くじけず、人から指さされようが、
好きで、でも周りの目や研究が進まないことに苦しんで、
それでもやり続けている人がいる。
そのような人たちが、大きな満足感と収入を得る。
ただし、きれいごとだけではなく、大きな満足感も、収入も得ることなく途中であきらめなければならない人も場合もある。
そして、科学的成果が出尽くしたら企業の研究室内で、例えば「生産の効率化」を研究する段階になる。
私が小学生の彼らに体験してもらいたいのは、
「苦しくて」
「先が見えなくて」
「世間から評価されなくて」
『それでもどうしても捨て去ることができないで苦しい思いで研究する』
『だからこそ、苦しみの中からしか絞り出せない本当のアイディアを生み出す』
『でも好きなんだ、という根拠のない希望がある』
『失敗して当然だから、どんなことでもやる』
できることならば、戦後の日本が焼け跡から経済成長してきたような、そのような体験をしてもらいたいと、私は思うのである。
その経験は、きっと彼らの「生きる力」の育成に役立つから。
それを思い悩んでも、だからといって、研究の進歩を今のままとどめることはできないし、良いことだとは全く思わないので、仕方ないことだけれど。
ということは、気づいてしまった私は、今よりもっと大きな夢の種をまかないといけない、のか?
答えがわかっているわけではないので、「今よりもっと大きな夢の種」を発見できる、創造性を発揮できる環境づくりをしないといけない、のか?
関連記事
-

-
「多様性の創り方・活かし方」の例
Princeton Groups / monyokararan[/caption] この記
-

-
コンテクスト(デザインの意図や理解したこと)を語る
Maestro Daniel Barenboimさんのワークショップの映像。 コンテク
-

-
ロボット教室の生徒諸君12~少し変える、「こんなのどう」って思いつく~
4ページ目を見てほしい。 大垣のMakerFaireで変形する車椅子や小学生発明家に出会っ
-

-
子供たちが(本当に)学ぶには、塾などで忙しすぎるのではないだろうか?
(もしかしたら何を言っているかわからない人がいるかもしれない・・・) 子供たちが(本当に)学ぶには
-

-
Web記事『小島慶子 子どもたちのお小遣い制廃止、その心は?』
『子供を前のめりにさせる(受け身にさせない)』 という視点では、興味を持ちました。
-

-
アンパンマンのあんが粒あんの理由
> 正義って、普通の人が行うものなんです。偉い人や強い人だけが行うものではないのね。 > やなせた
-

-
「いい話」を求めてます?
> 今日は天気がいいね。 > ある小学校長 (折々のことば 選・鷲田清一) 哲学者鶴見俊
-

-
「教育の義務」は親にある。「満足するまで学ぶ楽しさ」は子供の権利。
引用記事を読んで。 ~~~~~~~ 何かのインタビューで、 中学生か高校生が、 「僕
-

-
「○○を勉強する意味がわからない」という言葉を聞きます
「○○を勉強する意味がわからない」という言葉は聞きます。 でも、その言葉の意味がまた、僕にはわ
-

-
成功と失敗をどういう風に表現するか?
日本「打ち上げ失敗」アメリカ「partial success」 pic.twitter.com/jW
PREV :
教えすぎない
NEXT :
妙な宿題に本気で答える