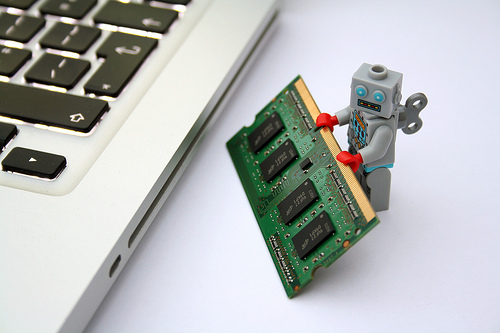10年先のロボット研究のテーマは何だろうか?
公開日:
:
最終更新日:2016/09/05
et cetera-life, 子供達の学ぶ心
東大から世界へ飛躍、自律型飛行ロボ「Phenox」がKickstarterプロジェクトを開始 – GIGAZINE http://gigazine.net/news/20140512-phenox/
ロボット教室関係で、私のアンテナに引っかかって収集した情報のメモ。
上記記事のヘリコプター(自立型飛行ロボ)は、コンパクトだからすごさが軽く見えるが、とてもすごいロボット。
日本のロボットが注目されたり、
その前にロボットを作っている人たちが発想力豊かにさまざまなものを想像しているのはいい。
魅力的。
でも、今の小学生たちが自分たちで作り出そうとする時期、
例えば、小学6年生が高校2年生や大学4年生になる、5年先、10年先に、
彼らが創造性を発揮できる状況が残っているだろうか?
もしくは新たなムーブメントが起こっているだろうか?
設計図通りに造るだけ、その範囲でつい実験をしたり、改良するだけでとどまってほしくない。
でも、
造船業や家電産業のように、大きな伸びがあった業界も、落ちる時期が必ずある。
その期間や落ち方は様々だけれど。
-----------------
スタート時点の話では、
ムーブメントの真っ最中は、というか、そのしばらく前から、
くじけず、人から指さされようが、
好きで、でも周りの目や研究が進まないことに苦しんで、
それでもやり続けている人がいる。
そのような人たちが、大きな満足感と収入を得る。
ただし、きれいごとだけではなく、大きな満足感も、収入も得ることなく途中であきらめなければならない人も場合もある。
そして、科学的成果が出尽くしたら企業の研究室内で、例えば「生産の効率化」を研究する段階になる。
私が小学生の彼らに体験してもらいたいのは、
「苦しくて」
「先が見えなくて」
「世間から評価されなくて」
『それでもどうしても捨て去ることができないで苦しい思いで研究する』
『だからこそ、苦しみの中からしか絞り出せない本当のアイディアを生み出す』
『でも好きなんだ、という根拠のない希望がある』
『失敗して当然だから、どんなことでもやる』
できることならば、戦後の日本が焼け跡から経済成長してきたような、そのような体験をしてもらいたいと、私は思うのである。
その経験は、きっと彼らの「生きる力」の育成に役立つから。
それを思い悩んでも、だからといって、研究の進歩を今のままとどめることはできないし、良いことだとは全く思わないので、仕方ないことだけれど。
ということは、気づいてしまった私は、今よりもっと大きな夢の種をまかないといけない、のか?
答えがわかっているわけではないので、「今よりもっと大きな夢の種」を発見できる、創造性を発揮できる環境づくりをしないといけない、のか?
関連記事
-

-
碇を下ろして根を下ろすこと、動き続けること
> 「根を下ろす」というのは、下からの声を聞き取り続けることで、そのためには舟底をものすごく薄くして
-

-
シミジミと感じる「幸福」は、どこにでもある
> われわれのそばを通り抜けてください、そしてわれわれの幸福を許してください! > ドストエフスキ
-

-
若い世代の選択を全面的に支持する
> どんな選択がなされても全面的に支持するのだと覚悟は決めておきたいものです。 > この覚悟こそ、
-

-
美しく散乱する部屋、あるいは多少の散乱ぐらいでへこたれない大らかな部屋
> 美しく散乱する台所、あるいは多少の散乱ぐらいでへこたれない大(おお)らかな台所が、私の理想です。
-

-
「人生は挑まなければ、応えてくれない。」
> 人生は挑まなければ、応えてくれない。うつろに叩(たた)けば、うつろにしか応えない。 > 城山三
-

-
「ロボット教室基金」の枠は作れる
> 破れてなかみのなくなった畳が畳であり、菜のない食事が食事であり、玩具のない遊戯が遊戯である。
-

-
日常、何を買うのかということも十分に政治的だ
> 俺から言わせれば、日々の生活のなかで何を買うのかということも十分に政治的だ。 > 後藤正文
-

-
「他人に与えてもらう夢は『娯楽』と呼ぶ」
岡野由美さんの「ぼんぼんすふぃあ」を読んでいて、 ポン、と膝をたたいたことがある。
-

-
今後30年間に変化するもの
今がベストなタイミング、AIは電気と同じような存在になるhttp://www.newsweekjap
PREV :
教えすぎない
NEXT :
妙な宿題に本気で答える